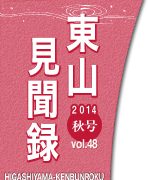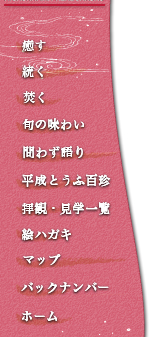霜月になれば京都の街のおまんやさんでは、お火焚き饅頭が店頭を賑わせます。程良く塩味が効いて、甘みがふわりと引き出されたあんこが美味しいふかし饅頭。ひと目でわかる火炎宝珠(か えん ほうじゅ)の焼き印が目印です。
お火焚き饅頭は、「お火焚き」のときにお供えするもの。お火焚きは寺社や火を使う仕事場などで、火への感謝を表す風習です。現在、一般では少なくなりましたが、伏見稲荷大社の火焚祭など市内の多くの神社では、それぞれ「お火焚き祭り」が営まれ、晩秋の京都の風物詩となっています。
「私らは10月末頃になるとお火焚き饅頭の季節がきたな、て思うねん。11月になったら、店頭に並べなあかんしね」と語るのは、すぐ近くの清水寺をはじめ、付近の神社なども御用達の老舗“おまんやさん”浪川菓舗の雪子さん。店主一久さんのお母さまです。
「お火焚き饅頭は、うちでは12月8日の針供養まで。よそでこしらえてもらうんやけど、“おこし”も一緒に用意します」とお話しいただいた一久さんの言葉にかぶせるように、雪子さんがこんなことを教えてくださいました。
「おこしは、三角形で柚子が香りまっしゃろ。三角は水を表現し、柚子は町屋同士の境界に植えられてきたように、延焼を防ぐ効果がある。お火焚きには、火の用心の意味も込められてるんやで」。
火への感謝とその力に畏敬の念を抱くお火焚き。地域によっては、お火焚き饅頭を“火の用心饅頭”と呼ぶこともあるそう。その素朴な“おまん”は、京都に住まう者たちに更けゆく秋を思い、冬支度を急かす、季節の移ろいを感じさせる庶民の味わいです。

本店は、大正の末頃の町家。今では珍しい、商品をお見せする「見せの間」のある「お店」です。
Information
浪川菓舗
東山区東大路松原上る辰巳町113
TEL:075(561)0933
|
|

「おまんに押すお玉(火炎宝珠の焼き印)がうまく焼き付かなかったものなどは、ご近所に配るんです。そしたらみんな声をそろえて、もっと失敗してや、って喜んでくれますねん。お火焚き饅頭は、ほんまに“地”に愛されてるなって思いますね」。 |