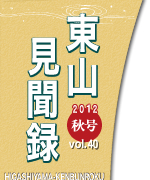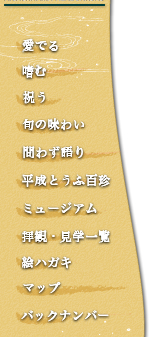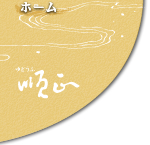歌舞伎演目「楼門五三桐(さんもんごさんのきり)」で、天下の大泥棒石川五右衛門の勇壮ぶりを如実に表現し、「助六由縁江戸桜(すけろくゆかりのえどざくら)」では、きっぷの良い男前な助六を誘う女性たちの愛情を比喩する小道具として、無二の役割を担う。落語や浄瑠璃などでも、しばしば登場人物のこころの動きが託されてきた“きせる”を、平成の今たったひとりで作り上げる職人が京都にいます。
「きせるは、喜世留なんですよね」。
日本で唯一となったきせる専門店『谷川清次郎商店』9代目の清三さんは、そう語ります。
「“喜びを、ひととき、世に留める”という意味です。杉田玄白が残したといわれている当て字なんですが、喜世留は自分好みに誂えた羅宇(らう)の色や文様、手触りを楽しみ、金具部分の美しさを愛でながら、香りを味わい、そのひととき酔う。喜世留は、嗜(たしな)みの文化なんですよ」。
羅宇とは、吸い口と雁首(がんくび)をつなぐ管の部位で、基本的には竹が使用されます。もともと谷川清次郎商店はその羅宇を製造していた煙管竹商でしたが、出入りの金具職人に跡継ぎがいないことを知った清三さんはその職人さんのもとへ通い、技術を修得。喜世留を最初から最後まで作り上げる職人となりました。
「西洋のパイプと違って、喜世留の火皿は小さいでしょう。ここに日本の文化が凝縮しているんです。実は、刻み莨(たばこ)は世界でも例を見ない日本で発展した莨の加工技術。その細さは髪の毛ほどのものもあったようです。その刻みを可能にしたのが、日本刀を作る高度な鍛冶技術でした」。
面白いことに、最近は若者が新しい目線で喜世留を和の文化として、ワインなどともにひとときを楽しんでいるのだとか。
形や素材、細工を愛で、香りと味わい、そしてその時間まで楽しむ。なるほど、古の傾(かぶ)き者たちが喜世留を手放さなかったわけです。石川五右衛門も、今と変わらない秋のまん丸なお月さんに紫煙を燻(くゆ)らせ、粋なひとときにひたっていたのかもしれませんね。 |
|

「喜世留は刻み莨を嗜むものです。嗜という字が、口と老と旨で構成されているように、歳を経てその味わいが深くわかるもの。私はそんな日本の粋な莨文化を伝えていければと、考えています」。
|