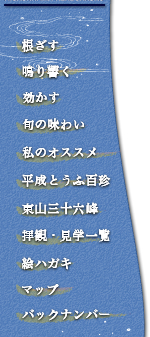京都特有の気候で“養生”させることで、心地よい音色へと変化します。
グォーン、グォーンと私たちの心にじんわり余韻を残しながら、百八つ撞かれる除夜の鐘。京都の大晦日の夜にはあちらこちらで、ゆく年を送り、真っさらな年の訪れを告げる厳かな梵鐘の音色が響きわたります。その音は、私たちにどこからか深い感動を呼び起こし、心静かにまだ見ぬ一年へと、そっと背中を押してくれるのではないでしょうか。
<およそ鐘の音は黄鐘(おうじき)の調べなるべし>
梵鐘の第一条件は音響であると言われます。徒然草に綴られたように、最も理想とされたのは国宝 妙心寺の黄鐘調の鐘の音。黄鐘調とは唐古律で用いられる優雅な調子のひとつで、この名鐘の引退にあたり、歴史的梵鐘と遜色ない音色を復活させたのが『岩澤の梵鐘』です。
「梵鐘の原料は、銅と錫です。鐘の命とも言える音色を決めるのは、その配合と鐘の厚み、そして火入れの作業。火入れとは、溶かした材料を鋳型に流し入れることです。やり直しがきかないたった一度の作業。この作業にかける時間や流し込み方で、すべてが決まってしまうほどです。温度設定とタイミング、何人もの作業者と気持ちをひとつにすることが大切で、何度経験しても、毎回その場にいるすべての人がただならぬ緊張感に包まれる時間です」と、岩澤の梵鐘の名を継ぐ岩澤一廣さん。
「鋳型から外し、バリを落としてもすぐには撞きません。数ヵ月から時には何年も、自然の温度変化にすべてをまかせる養生が重要なのです。特にここ京都は一年の温度変化が大きいため、良い音色へ変化させるのには絶好の土地なのです。」
音色への飽くなき探究は、職人の世界でありながら、科学的見地からもアプローチをされています。「音響学の第一人者青木一郎先生の学説を実験的に取り入れ、指導を仰ぎながら全国を廻って様々な音のデータを集め、人間に心地よい聞こえを追い求めてきました。現在では生活サイクルの多様化により、お寺の鐘の音を耳障りと感じる人もいらっしゃいますので、蓄積したデータを活かし、日常に馴染む響きの鐘を制作したこともあります。いずれにしても、私どもの仕事はお寺さんや檀家さんの気持ちを鐘の音に託すこと。科学的な視点だけでなく、積み重ねた経験が重要な意味を持つことにかわりありません」と語る岩澤さんの横顔は、職人そのもの。歩みを止めない進取の伝統技術の調べは、大晦日に耳をすませば、あなたにも心地よく響くかもしれません。 |
|

「撞きはじめて10年くらいは、人間で言うとまだ子どものようなもの」とのこと。「心が洗われる梵鐘の音色がうるさく感じてしまう今の感覚に、警鐘を鳴らしていかなければならないと感じています」とおっしゃっていました。 |