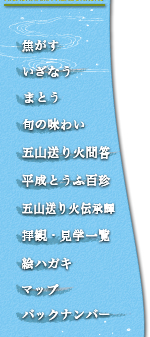あっさりのイメージが強い京都に、ソース文化が存在することをご存じですか?
さかのぼること、大正末期。文明開化で洋食文化が庶民にまで広がった頃、ウスターソースをたっぷりぬった一銭洋食が流行したり、昭和初期には、地ソース企業が十社以上加盟していた京都ソース協同組合が存在していたほど。今でも六社が残る隠れたソース地域でもあります。
その中でも、当時、東京−大阪間の所要時間を大幅に短縮した歴史的超特急「つばめ」の名を冠した、地ソース『ツバメソース』が今回の舞台です。
ソースの香りにふらりふらりとつられて歩み進めた場所は、京都市南区東九条。全国にファンを抱える創業八十余年のツバメソースは、従業員六名、すべてを手作業で生み出す企業です。
「何と言っても、ソースの魅力は“食”を引き寄せることですね」。そう語るのは、創業者の甥っ子にあたる勝田裕さん。ツバメソースを使うお好み焼き屋さんの中には、味を真似されまいとソースのラベルを剥がして使うところもあるそう。その味の秘密に迫ると勝田さんは「うちは、何も特別なことをしているわけではありません。ただ、お客さんにいつも同じ美味しさを届けることを心がけているだけ。例えば、八ツ橋にも使われている独特の香りのある桂皮。手に入りにくくなっても、辛みの強いベトナム産にこだわりたいですし、季節によって味の差が出にくい地下水をずっとくみ上げています。」と赤裸々に。「ソースの味の違いを知るなら、キャベツの千切りにかけてみると歴然。夏なら、冷やしたトマトとの相性は抜群。その時はぜひ、ツバメで。」と語るクセのない人柄は、懐(ふところ)深い味わいのツバメソースそのまま。
京都慣れした方のおみやげにもぴったりのツバメマーク。ぜひお見知りおきいただきたい逸品です。
|
|

京の地ソースらしく、「うちのソースの七割が京都で消費されています」とのこと。また、「ソースの原料になる香辛料は、漢方薬の材料といくつも重なっています。昭和初期の頃は、薬局にソースが陳列されていたとか」という意外なお話も。 |