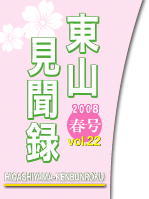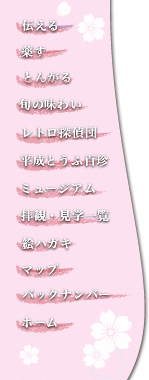さやさやと春風が吹く、京都・西山の竹薮。丹念に手入れされ、ジュウタンのように平かになった地面を割って、ぷっくりと、とんがった筍(たけのこ)がわずかに顔を出します。やわらかで、自然の匂いがふわ〜っと薫る旬の味。そんな京都の“旬”を知ってもらおうと、上田耕司さんが錦市場の八百屋の二階で始めた店が、その名も「やお屋の二かい」です。
「昭和5年、祖父の代から錦市場で八百屋をやってきました。さらにさかのぼれば、明治15年錦市場の乾物屋さんに間借りして旬を商ってました。そんななかで、なんとか京野菜の美味さを知ってもらいたいと、レシピを配布したり、試食をしてもらったりと、いろいろ工夫を重ねて行き着いたのが、八百屋が食べてる野菜をお客さんにも食べてもらうことです。とりわけこだわっているのは、春のたけのこと秋の松茸です」。
そんな上田さんの目にかなった筍は、4月から5月にとれる旬のもので、そのなかでも西山の塚原にある竹薮のものが最良だそうです。春が長けるころ、二かい…もですが、本業の八百屋の店内に朝掘りの新鮮な筍が並びます。ただ、慣れない方はその値段に驚くかも!?
「ウチの筍は値が高いんです(笑)。でも、これはしようがない。日本全国どこにでもある孟宗竹の筍なんですが、これが、どこにでもある筍とは違う。125年、三代も四代にもわたって契約してきた農家が、春夏秋冬、肥えをやったりワラをしいたりと絶えず世話をしている竹薮の筍なんです。筍は実に繊細な“京野菜”で、何年ものの竹の子かによって味が変わってくるので、農家では一本一本の竹に番号を打って管理しています。筍の“戸籍”を作っているほどです」。上田さんが塚原の筍を最良とするのも、繊細な筍が美味しく育つ理想的な条件を満たしているからで、その条件には土壌ばかりではなく、風向きまで含まれているとのこと。まさに大地が作り出す芸術品ですね。
ところで、上田さんに筍の扱い方について教わりました。
「とにかく、家に帰ったら筍をすぐにゆがいてください。筍は生きて成長を続けています。どんなに良い筍でもそのままにしていたら固くなってしまいます。その成長を止めるために、ゆがくわけです」。
ゆがいた筍の料理法はいろいろありますが、筍ごはんにしてみませんか?
「昔の京都の家庭では、雛祭りにはちらしずし、5月5日の端午の節句にはたけのこごはんを食べました。家族みんなが楽しく食べられる料理法です」。
|
|

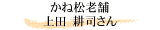
「店には並ばない、いや、並べられない“幻の筍”というのがあるんですよ」。梨かリンゴのように甘い味がする筍ですが、自然の条件にとても敏感で、去年出たからといって、今年出るかどうかは全くわからない。「…だから、商品には出来ないんです」。
|