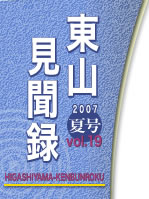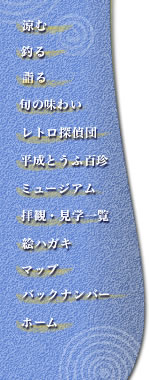|
いよいよ夏本番!釣り好き、アユ好きの人にはこたえられない季節です。そんな季節に、丹波・美山町から一通の手紙が届きました。清らかな流れとしたたる緑の里で、晴耕雨読ならぬ晴釣雨書の暮らしをン十年、『晴れて丹波の村人に』、『芦生奥山炉辺がたり』などの好著でも知られる釣り人・森茂明さんからです。
山といえば富士、花といえば桜、日本を代表する風物を二つあげたが、三つ目は「魚といえばアユ」といいたい。
アユの字は魚偏に「占」と書く。記紀(『古事記』、『日本書紀』)に登場する神功皇后が新羅に遠征の折、武運の占いに出てくる魚がこれで、古いのになると、神武天皇が東征の際、神のお告げにより、かめと壷を丹生川に沈めたところ、吉兆を知らせるこの魚が浮かんできて、橿原宮で即位されたという。代々天皇の即位儀礼に掲揚される七種の御旗のうち、五尾の魚、かめと壷、万歳の二文字が刺繍された万歳旗がこのうちの一つである。さらに古くなると、縄文時代早期の土器の表面についた文様は、縄目文とばかりかぎらず、鮎の背骨を押しつけた跡だという考古学者もある。
山背という陸から吹く風とは逆に、海から吹く南風のことを「アユの風」とよぶが、この風が吹きつける三月弥生、日本列島の各河川に若鮎が溯上する。しかし、残念、日本の川にはたくさんのダムが造られていて、溯河も降海もかなわぬ鮎の保護増殖を釣り人のために、毎年びわ湖の湖産鮎がアユ苗として放流されている。鮎はわが国をはじめ、朝鮮半島から中国、台湾、中越国境までの東アジアに分布している。だが、魚がすめるのは山が海岸線近くまでせまり、水清冽にして大小の石が転がる山紫水明の環境が条件で、早く成長して味がよくなるためには、餌となる石垢の珪藻が必要となる。大河でも、石が少なく、水が濁った黄河や長江には生息しない。
太平洋戦争期、鮎のすむところ全て日本の勢力圏たるべしと、アユの縄張りと大東亜共栄圏とをはきちがえた人があった。あった。神功皇后の故事以来、鮎はいつも外征のつどその引き合いにかつぎ出されて、味がよいのをよいことに後味の悪い迷惑をかけている。
平安時代、京都嵐山の桂鮎は、桂女の頭にいただく桶に入れられて、御所の内裏へ献上鮎として貢進された。
桂女や新枕する夜な夜なは
とられし鮎のこよひとられぬ
【頼政集】
かつらより鮎釣る小女引きつれて
今ぞ雲居の日次知るらむ
【弁内侍日記】
今年も鮎の季節が訪れた。塩焼き、背ごし、鮎めし、鮎寿司、鮎の開き干し、どれもこれも嗜好の絶品だが、内臓を塩漬けしたウルカは格別で、とかく日本酒との相性がよい。
|