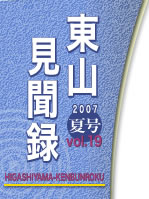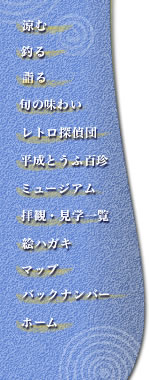|
「地球温暖化」「異常気象」という言葉を夏が来るたび聞くようになりましたが、そこに危機感や不安感を感じる気力が無くなるくらいに、毎日、暑い日が続きます。エアコンや扇風機が無かった時代の人間は、どうやって炎暑をしのいでいたのかと思いますが…
庭に水 新し畳 伊予簾
数奇屋縮みに、色白の美女
狂歌に詠まれているように、意外と粋に夏を楽しんだようです。その粋を現代の夏に楽しもうとお訪ねしたのが、東山区東大路松原上ルにある「伊吹すだれ店」です。畳敷きの店では、店主の伊吹忠夫さん、息子の忠弘さんが仕事の真っ最中。すだれの素材になるのは主に、琵琶湖で刈り取られたヨシやガマです。
「よく似ているんですが、ヨシとアシという二つの植物があります。ヨシというのは柔らかくて加工しやすい。アシの方は堅うて加工には向きません。『良し悪し』という言葉は、このヨシとアシに由来するのやそうです」。古い木製の製簾機でヨシを編んでいた忠夫さんが教えてくれました。「すだれは日光をさえぎるので、部屋の温度が上がるのを防げます。だからクーラーもそれほど必要なく、省エネで“地球にやさしい”んです」と忠弘さん。
店内に見られるのは、ヨシ、ガマ、竹、そして煤竹や綿糸。いずれも長い歴史の上でさまざまな恩恵をもたらしてくれた植物ばかり。そんな植物と人間が共存できた時代には、「地球温暖化」も「異常気象」も無縁だったでしょう。
「近年、ヨシやガマが手に入りにくくなりました…。昔は冬の農閑期、農家のお爺さんやお婆さんが琵琶湖に小舟を浮かべて刈り取ってたんですが、暮らしが豊かになってその作業をしてくれる人がめっきり少なくなりました」。忠夫さんがしみじみ語るように、夏の情緒や風情は、いつの間にか消え去ろうとしているのかもしれません。
|
|
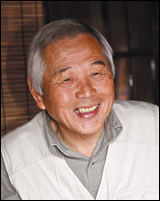
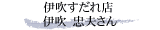
父子で作るのはすだれに限らず、御座敷すだれやよし障子なども。そこには丈夫にいつまでも使える技が求められます。「すだれの場合、吊しっぱなしでも十年くらいは十分持ちます。具合が悪くなれば修繕して、長く愛用いただいてます」。 |