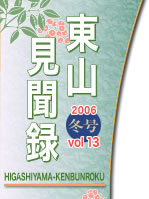喜び、悲しみ、さまざまな想い出を残し、一年が過ぎてゆく大晦日。毎年テレビで除夜の鐘を聞くという方も、今年は京都の総本山知恩院で、巨大な梵鐘を見上げつつ、大勢のお坊さんが撞く響きを耳にして、清らかな心で新年を迎えてみませんか。
「日本三大梵鐘の一つに数えられております知恩院の梵鐘は、寛永年間に鋳造された”洪鐘“と申しまして、高さ一丈八寸(3.3m)、口径は九尺二寸(2.8m)、重さは一万八千貫(約70t)あります。除夜の鐘は、子綱を左右八人ずつ、中央の主綱に一人、総勢十七人が掛け声とともに撞きます。暮れに”試しつき“というリハーサルを行ない、皆で息を揃えて大晦日の本番にのぞみます。なにしろ大きな鐘ですので、数回撞くごとに撞き手は交代いたします。音色はドォ〜ンと低く迫力のある響きです」。宗祖・法然上人の大きな絵像の前で、鐘の音のように低音の効いた声で朗々とお話くださったのは、法務部長の南忠信執事です。
お話に出た洪鐘とは、大きな鐘という意味だそうです。なるほど、重要文化財に指定されている大鐘楼で間近に見上げると、まさに圧巻です。江戸の昔、山上までこの洪鐘を運び上げるのにどれほどの人々が従事したか…そこに想いを巡らすと、総本山知恩院に寄せられた信仰の篤さが感じられます。
「故老の説によると百八の除夜の鐘は、旧年の内に百七まで撞き終え、残りの一つを新年になってから撞きます。百八あるといわれる煩悩と同じ数だけ撞きます。煩悩の数え方はさまざまあり、身・口・意の煩悩を合わせると八億四千の煩悩があるという数え方もされます。数ある煩悩なかには”眠気“というのもあり、仏法修行の僧侶にとっては眠気は”怠け“に通じます。読経の時に木魚を叩きますが、昔の人は魚にはまぶたが無いと考えていました。木魚を叩くことには、まぶたが重くなって、眠気に負けてしまわないようにという意味が込められているのです」。
数万人の参拝者が見守るなか、静寂の東山三十六峰に百八つの鐘が響き、眼下の京都の街を浄めてゆく除夜。心の目もパッチリと見開いて、素晴らしい新年を迎えたいですね。 |
|

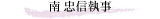
「長らく自坊をお守りしてきて、今春、総本山に奉職することとなりました。12月27日の『試しつき』は目にしましたが、いよいよ今年は除夜の鐘を」。

|