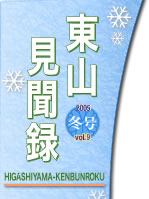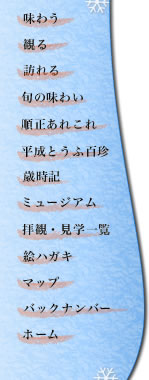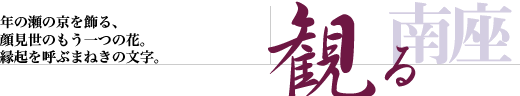鴨川に師走の風が吹き出せば、いよいよ京の人々、いや、日本中の歌舞伎ファンが待ちかねた、東西の人気歌舞伎役者が勢揃いする四条南座の顔見世の季節です。特に今年は十一代目市川海老蔵さんの襲名披露。昼の部には歌舞伎十八番の『暫』と舞踊『お祭り』。夜の部では『助六由縁江戸桜』で、病気療養から復帰した父 團十郎さんとの共演です。歴史の長い南座の顔見世でも、團十郎と海老蔵の共演、そして二人の名を書いたまねきが同時に上がるのは史上初めてです。
その記念すべき興行に、墨痕鮮やかにまねきの文字を書くのは、書家・川勝清歩さんです。「顔見世興行が大当たりで席が隅々まで埋まるようにと、まねきは肉太の文字で隙間の無いように書くんですよ。まねきでお馴染みの文字は、江戸時代から伝わる“勘亭流”と呼ばれる書体で、長らくまねきを書いていた師匠の竹田耕清さんから伝えられました」。歌舞伎の役者さんたちが師匠の芸名から一文字貰うように、川勝さんの雅号“清歩”も、師匠の耕清さんから一文字譲られたものです。
艶やかで雨に濡れてもにじまない、この秘訣は独特の削り墨。「削り墨を一晩水に浸して、それを大きな当り鉢とバットで摩るんです。まねきは大きいですからね、バットを使わないと間に合いません」。
「海老蔵さんの蔵の字とか、團十郎さんの團の字は、画数が多くて意外に書きやすいんです。実は一とか七のように画数の少ない文字の方がバランスが取りにくくて難しいんですよ」と、人には分からない川勝さんの苦労話。
「毎年『書くのが恐いなぁ』と緊張します。でも書き終えて南座にまねきが上がる時、『あぁ今年も大仕事をやり遂げた…』と喜びがこみ上げてくるんです」。そう語る七十一歳の川勝さんの笑みに、顔見世の歴史が漂っていました。 |
|
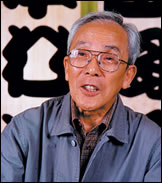
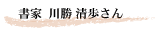
| 「小学生の時から図工が好きで、それがこの道に入ったきっかけです」と語る川勝さんの趣味は、模型造りと小旅行。川勝さんが書き上げたまねきの下を潜(くぐ)る時、劇場のお客さんたちも、時空を超えて“小旅行”へと旅立ちます。 |
|