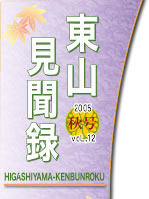両替町は、その名でわかるように江戸時代からのビジネス街。ビルの谷間を人と車が頻繁に行き交う風景のなか、静かな潤いをもたらしてくれる空間があります。江戸時代初期から十一代も続く唐紙の工房〈唐長〉が、昨年から設けた直営店です。店内に並んでいる大小さまざまな和紙、ポストカードには、江戸時代から大切に使われてきた版木を用い、木版画の手法で草花や幾何学模様が摺られています。
「唐紙の文様は、草花の姿をシンプルに表現した優れたデザインです。そこには奥深い魅力があるのですが、現代の生活では唐紙が利用される機会が少なくなってきました。このように特殊化された唐紙の世界のよさを伝えるために、国内、海外の人々と積極的にコミュニケーションをはかったり、展覧会を開いたり、さまざまなコラボレーションを展開して、時代に生かせる道を探究してきました」。と語るのは当主の千田堅吉さん。初代が唐紙を製作した桂離宮、二条城などの修復に携わるかたわら、新たな可能性を探ることに挑戦してきました。
唐長の初代が生きたのは江戸時代初期。京都に王朝文化が華やかに復古し、本阿弥光悦や尾形光琳が活躍したころです。光悦、光琳と唐長初代との交流から、さまざまな版木の意匠が考案され、また光悦が出版した「嵯峨本」の表装には初代が作った唐紙が用いられました。
四百年前、伝統文化と先進のセンスから生まれた意匠−。「近代、京都の文化財が海外に紹介されるようになると唐紙も世界から注目されるようになりました。花の連続模様で知られるルイ・ヴィトンのデザインも、唐長の唐紙文様とよく似ていますねぇ」。唐紙を巡る人と人、心と心の絆が世界へと広がった一コマです。
伝わっている版木の数は約三百六十枚。しかし、色彩の組み合わせは無限大です。武士から転身した初代のように、ビジネスマンから転身した十一代目も、幅広い交流から唐紙の可能性を開拓し続けています。 |
|

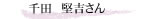 今後の夢は…?「江戸時代の仕事場の雰囲気に戻してみたいですねぇ。便箋なんかをお客さんの注文に応えて、私が工房で作る。そんな気軽な雰囲気に」。
今後の夢は…?「江戸時代の仕事場の雰囲気に戻してみたいですねぇ。便箋なんかをお客さんの注文に応えて、私が工房で作る。そんな気軽な雰囲気に」。
 |